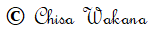注釈(*)をクリックすると解説ページに移動します。別窓で参照したい場合はこちら。
1.赤子のような人参果
流砂河を渡りきった一行はさらに西へと向かった。あまり人が立ち入らぬ地であるのか、自然が美しく、穏やかで瑞気が立ちこめていた。
それもそのはずで、三蔵たちは西午貨州<さいごかしゅう>に足を踏み入れていたのだった。ここには五荘観という道教の寺があり、世界を探しても他には生息していないという人参果がある。香りをかげば三六〇まで生き、実を食べれば四万七千まで生きられるという。一万年で三〇個しか実にならぬというから、非常に希少価値のあるものだというのがわかるだろう。
この宝果をめぐり、ちょっとしたいざこざが起ころうとは、三蔵にとってはまさに寝耳に水であった。
『万寿山福地 五荘観洞天』と書かれた門の前を通りかかると、付近でこそこそと話しをしている童子が2人いた。
「あのお方では?」
「いや、だけど、連れている者たちが恐ろしい顔つきをしているぞ」
「そんなこと言ったって、こんなところを通りかかる法師なんてしれてるじゃないか。見過ごしたら大仙になにをいわれるかわからない」
ちょうど宿をとろうとしていた三蔵は馬から降りて、童子に声をかけた。
「わたくしは東土より参った者です。宿をお借りしたいのですが、ここのお弟子さんですか」
「は、は、はい。そうです。もしや、唐の国王の勅令で経典を天竺まで取りに行かれるお方では?」
「その通りですが、どうしてそれを?」
「私どもの師匠が出かける前におっしゃられたのです。五〇〇年前に盂蘭盆会で知り合った如来仏のお弟子さまが通りかかるので、留守中にもてなしをし、お引き留めするよう申し使わされたのです」
「五〇〇年前だって?」悟空が素っ頓狂な声を上げた。とはいっても、ここ西午貨州の者たちは五〇〇歳生きるのが普通である。悟空が驚いたのは別のことであった。
「お師匠さんの前世が如来の弟子だったとは、驚いた。お師匠さんも実はなんか悪いことをして下界へ落とされたんじゃないの?」
と、悟空がいうのもあながち間違ってはいない。釈迦の二番弟子でありながら、教えに背いたために転生させられたのだった。
「残念ながらわたしにはその記憶はないのだよ。道士のお名前はなんとおっしゃられるのです?」
「鎮元大仙です。只今、元始天尊(*1)からのお誘いで上清天の弥羅宮へ講釈を聞きにいっておりますので、お帰りになるまでおくつろぎください」
ひとりが馬の手綱を取り、ひとりが荷物を持った。
「さ、こちらへ。わたくしは清風で、こちらは明月と申します。他にも46人の弟子がおりますが、大仙のお供で出払っていますので、わたくしどもになんなりとお申し付けください」
「なんだか知らないが、今までで一番待遇がよさそうなところだぞ」
気をよくした悟空は先頭を切って門をくぐっていった。
本堂へ通されると三蔵は香をつまんで礼拝した。立派な道観をぐるりと見渡して、ふと気づいた。
「三清(*2)、四帝、羅天の神をまつっていないのはなぜです?」
「大仙より位の低い神をまつることはできません。三清は気を許す間柄、四帝は馴染みの友で、九曜や元辰(*3)は下の身分になります」
「なんと、それはそれは、たいそう修行を積まれたのでしょうね。わたくしの前世を知るはずです。わたくしどもが通りかかるのを予言されていたのもどうりで、納得がゆきました」
清風と三蔵が話している間、明月は暇をもてあましている三蔵の弟子たちを別室に案内して休むようにいった。
そして、お茶を出し終えた清風と合流して大仙に言付けされたように、金撃子<きんげきし>という金の棒と、絹の袱紗<ふくさ>を敷いたお盆を持って庭へ出た。あの人参果を三蔵に食べさせてあげるためだ。
人参果は五行を忌む。つまり、金にふれれば落ち、木にふれれば枯れ、水にふれれば溶け、火にふれれば焦げ、土にふれれば土の中に入ってしまう。そんなわけで用意が必要だったのだ。
繊細な果実ゆえ、ふたりの弟子たちは慎重に実をたたいて落とし、お盆の上で受け止めた。大仙に言われたとおり、2つを三蔵の元へ持ってきた。
「これは人参果というものでございます。へんぴな場所で大した物はご用意できませんが、これを差し上げるよう大仙に言付かっておりますので、どうぞお召し上がりください」
「こ、これは!」
三蔵は恐れおののいて思わず目を背けた。
人参果はまるで生まれたばかりの赤子のような形をしていたのだった。手足から目鼻口まで備わっている。それを食べろといっているのだ。
「ここでは人の子を喰らうのが習わしなのですか。このような立派な道観をかまえておきながら、どういうことなのでしょう。いくら道教と仏教と門が違うとはいえ、このようなことは許されません」
「いえいえ、これは赤子ではございません。似ていますが、のどを潤すほど果汁がある実です。九千年かかって実を付け、さらに千年おくと、このように真っ赤に熟成するのです。観音菩薩も食されたことがあるんですよ」
「結構です。下げてください」
気分が悪くなった三蔵を見て、しかたなしに童子たちは盆をさげた。
人参果はひとたび叩き落とされると、長い間置いておくことはできない。どうせ食べられなくなるのならと、ふたりの童子は一個ずつ仲良く食べてしまった。
人を食うことを想像しただけで吐き気がしてきた三蔵であるが、赤ん坊そっくりな人参果を見て、覚えているはずのない赤ん坊の頃の様子が脳裏をよぎり、慟哭が激しくなった。
それは産み落としたばかりの三蔵を、実の母親が川に流している場面だった。母の血で染まった赤子が産声をあげている――。
三蔵は深く息をついた。生まれながらに苦行を強いられるのも、前世の悪行の報いであるのか。
三蔵が自分の出生について詳しい話しを聞かされたのは18歳の時だった。流されてきた赤子を救い出したのは金山寺の長老、法明和尚で、幼な名を江流と呼んで育ててくれた。捨て子であるというのは誰もが知るところであった。
小さい頃から説法を聞いてきた三蔵は、他の誰よりも仏の教えを理解していたので、若い僧から嫉妬され、「どこの馬の骨ともわからぬくせに」と陰口をたたかれることもしばしばあった。
悟りを開くということは、この世の欲をすべて捨てるということである。家族、友人、出世、金、住まい、食欲、性欲……。天涯孤独の三蔵は、一番近いところにあるというのに、まだ見ぬ家族や、心許せる友の存在というのに、ある意味、渇望していた。迷いが生じるのはまだまだ修行が足りぬせいだと思うようになっていた。
18歳になったとき、法明和尚は玄奘という法名を与えて仏門に入らせると、托鉢僧となって修行に出るよう申し渡した。若い僧たちが「やっぱり師匠も身分の卑しい者はここには置いておけないと思ったんだろうな」と噂しているのを耳にした。一生法明和尚の弟子であり続けると思っていた三蔵は少なからずとも落胆した。
そして、旅立ちの時、三蔵は法明和尚に見送られて出発した。そのとき渡されたのが、川から流されたとき来ていた襦袢<じゅばん>と、ふところに入っていた血文字の書であった。
そこでようやく三蔵は誰の子であるかを知ることになった。(*4)