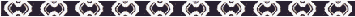

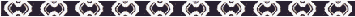
人類が誕生して間もない頃のことであった。奈良県の天理市あたりにじいやとばあやがいた。契りを交わして三十年が過ぎても子供を授からずにいた。前世は人間ではなかったであろうが、きっと、悪行を重ねていたに違いない。だからこのような報いを受けるのだと、嘆き悲しんでした。
ただただ、毎日瓜をせっせと育てるばかりであった。ある日、畑に行くと食べてしまうには惜しいほどの美しい瓜を見つけた。じいやは家に持って帰るといった。
「この玉のように美しい幼子がいたらどれだけうれしいだろうか」
「ほんにまぁ、食べるのが惜しいわい」
「同じことを考えておるわ」
ふたりはもいだ瓜を戸棚にしまっておくことにした。その晩、寝ていると戸棚から物音がした。どうしたものかとじいやが戸を開けると、なんともかわいらしい姫君がいた。
「ばあさん、これはいったい」
「瓜から生まれたんですよ。わたしたちが子供のように大事に大事に瓜を育てたから、前世の悪行をお許し下さったのでしょう」姫君は日が経てば経つほどに美しくなった。姿顔立ちのみならず、人柄も文才も知恵もこの世にないほど優れていた。
噂を聞きつけた国の守護代は后にしたいと、手紙で申し立てた。じいやとばあやは大変喜び、支度をはじめた。
「いいかい、人さらいにあったら困ったことになる。扉は開けてはならないよ」
じいやとばあやはたっぷりと念を押して出かけた。近所に住む世にも醜い女がいた。同じ貧しい家の者でありながら、美しい女だけが幸福になれるのは不公平に思った。それに、あの女は瓜から生まれたというではないか。醜女は他人の、特に美しい女の、幸せは我慢ならなかった。
醜女は瓜姫を誘い出すと、遠くの木につるし上げた。それだけでも清々したのだが、せっかくだから守護代の元へ出向いてみたいと思った。顔を隠して迎えのかごやに乗った。瓜姫を見つけないように、遠回りの道を教えたのだが間違った道を来ていた。上の方ですすり泣く声が聞こえてきた。本物の瓜姫を見つけると、醜女の正体はばれた。
「こんな女と間違えるなんてひどすぎますわ」
もっともだと、迎えの者は瓜姫にわび、このことを守護代に秘密にしてもらうよう願った。迎えの者達は話しあい、醜女を始末することにした。あまりの理不尽さに醜女は、女の武器を使って泣きながら「許してほしい」とすがりついて謝罪したが、男達の胸をうつにはほど遠かった。男達はススキで生い茂る野原に連れ込むと容赦なくずたずたに切り裂いた。この世に醜い女が存在してはいけないと言わんばかりに……。
そういうわけで、今でもススキの根は赤いのである。