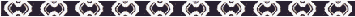
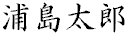
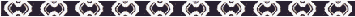
昔、丹後という国に浦島太郎と申す者がいた。釣りを生活の糧にしていた浦島太郎は毎日沖へ出ては釣り糸を垂らしていた。
ある日のこと、いつものように釣りをしていると亀を引き上げた。大きな亀であったので精力が付きそうだったが、万年の命を早々に絶ってしまうのは可哀想だと思い、逃がしてやった。幾日か経って、沖に船を出すと女がひとりで船に乗っているのを見つけた。
「あなたのようなか弱い女性がどうして恐ろしい海にいるのです?」
「わたくしの乗っていました船が転覆し、ある人に助けてもらい、こうして小さな船を貸していただいたのですが、迷ってしまったのです。どうかわたくしを島まで送り届けてはもらえないでしょうか」
浦島太郎はひとりにしておけないと思ったので、こちらの船にくるよう手をさしのべた。女の住む島までは十日もかかった。
「寄って行かれてはどうですか」と、女が誘うのでお言葉に甘えることにした。
女が連れてきたところはそれはもう立派な屋敷だった。銀の塀に金の屋根瓦。天上の地にも勝る居はないであろう。
「ここはもしや……」浦島太郎はじいさんから聞いていた遙か遠くの海にあるという城を思い出していた。
女は城へ案内すると四方向戸口で囲まれた場所に連れてきた。東の戸を開けるとそこだけ春の空間が広がっていた。北の戸、南の戸、西の戸、それぞれの四季が存在していた。
「どれになさいますか」
「どれって?」
「あなた様のお好きな部屋でどうぞ」
「なぜこんなことを?」
「わたくしはあなた様に助けていただいた、いつぞやの亀でございます。ですからあなた様の前に現れたのです。やはりあなた様は心優しかった。わたくしをここまで送り届けてくださったのですから。さぁ、遠慮なさらずに」このような高級かつ風情のある場所で、浦島太郎は何日も何日も、時がたつのも忘れて遊んだ。
しかし、そんな素晴らしい日々でも三年過ぎると飽きてきた。
「父も母も心配しているでしょう。そろそろ帰ろうと思うのですが」
「そうですか」
女は寂しそうに言って、
「それではこれをお持ちになってください」
女が渡したのは小さな重箱だった。
「ただし、なにがあっても開けないでくださいね」
開けるなというものを持たせるとは変な女だと思ったが、浦島太郎は喜んで受け取った。自分の国に戻った浦島は異変に気づいた。すっかり様が変わってしまっているのだ。見慣れた藁葺きの民家はなく、瓦の家がほとんどを占めており、道もわからなくなるほどだった。
きっと違う島に来てしまったに違いない。
浦島太郎は何日も船で漂流したが自分の知る国には着けなかった。腹が減ってどうしようもなかったので重箱を開けてしまった。するとたちまちにして鶴となってしまった。
なぜ、なぜ、あの女はこのような仕打ちを……。竜宮城へ帰すと女の前に降り立った。
「重箱を開けてしまわれたのですね」
「腹が減っていたんだ。重箱の中身といったら食いもんに決まっている。開けてなにが悪い。鶴になると誰が予想するか」
「あなたはここで過ごした日を三年と思われているかもしれないですが、本当は七百年も過ぎているのです。人間は七百年も生きてはおれません。その時間を重箱に閉じこめたのです」
「だから鶴か……」
「そうです。鶴は千年の命を与えられています。あなたが死んでしまわないよう鶴になることをわたくしは願ったのです」
こうして浦島太郎は残りの三百年を亀と共に過ごした。