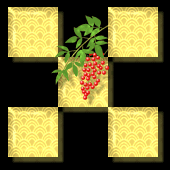
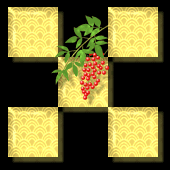
睦月は夜の都を足早に闊歩していた。火の雄叫びを聞いたからだ。火は大変獰猛で、大食漢で、太古の昔に神が人の子に使う許しを与えた事を悔いたものの一つである。火はいつも行儀がいいとは限らない。その扱いを間違えれば、確実に人の子の生命すら危なくするものなのだ。
少し離れた辺りで、小さな火の光を睦月は認めた。そしてそれはゆっくりと野に放たれようとしていた。
ぱちん…。
睦月は指を小さくならした。そしてゆっくりと小さな子をあやすような仕種で手を動かした。するとその小さな炎はさらに小さくなり、やがては消えた。しばらく悪態をつく声が近くから聞こえてきたが、やがてその声も遠ざかり辺りは静寂が訪れた。
睦月は先月のお勤めのさなか、自分のいる日の屋を見上げて心から願う声を聞いたのだ。それはこの都を治める帝の声であった。
「偉大なるアマテラスよ。貴女様がまだこの都を見捨てずにお守り下さっているなら、どうか私にお力を…。」
睦月は燃え盛る日の羽のなかで、この帝のつぶやきを聞くとは無しに聞いていた。この数年の飢饉で人々の暮らし向きはすっかり苦しくなり、流行り病が横行しているのだと言う。さらに夜の街には旅行者狙いの追い剥ぎがうろつき、カモがいない時は裕福なお屋敷に火をつけ、火事場泥棒を働くと言う。
「偉大なるアマテラスよ。貴女様の御子息は深い山々に囲まれた地でひっそりとお暮らしの事と聞く。どうかそのお方のお力を我に与えよ!さすればこの都の民は救われます!」
睦月は、それももっともだ、と思った。日暦なら火はこの燃え盛る太陽の炎だけでなく自由に操る事ができた。流行り病は自分の作る薬と、薬師の如月で治す事ができるだろう。飢饉続きの田畑には霜月がより質のいい土と種を恵むだろう。
一月のお勤めを終わらせた睦月は、早速帝のもとを訪れた。
「私は日暦睦月(ひごよみのむつき)と申すもの。帝にお目通り願いたい。」
帝はこの胡散臭い訪問者を煙たそうに見つめたが、睦月がぱちん、と指をならしたとたん、小さな炎が幕の様に地面から立ち上り、そこに自分の顔を浮かび上がらせた事に恐れをなした。火の中に浮かんだ帝は言った。
『偉大なるアマテラスよ。貴女様の御子息は深い山々に囲まれた地でひっそりとお暮らしの事と聞く。どうかそのお方のお力を我に与えよ!さすればこの都の民は救われます!』
「貴方様は!」
睦月の正体に気がついた帝は、涙を流して彼を迎えた。
そして数年の月日が過ぎた。付け火をするものはいなくなり、飢饉も去ったかに見えた。流行り病もすっかり下火になった。
「なあ、日暦の…。」
「なんでございましょう?帝。」
睦月は帝の差し向いに腰をかけ、ちらりと帝を一瞥した。
「余は幸運にもそなたと知り合う事ができ、こうしてそなたと話をする事ができる。」
帝は控えていた女官に目配せをして、静かに庭に向かうふすまを開けさせた。庭には2羽の見事な尾長が梅の枝に止まり、そのきらびやかな尾羽を風になびかせていた。
「余はもっとそなたの力を借りたいのだ。この都だけでなく、東の地を制圧し、北の方にも攻め上る。この都だけでなく大きな地を手にいれたくないか?そなたは政に手を染めるつもりはないか?」
「この私に?人の子の政をせよと?人々を制圧し、君臨せよと言うのか?」
睦月はにやり、と笑った。
「そなたが望むなら、この屋敷を進呈しよう。全ての調度、全ての家臣をつけたままだ。」
「興味はない。」
「同じような邸宅を全ての御兄弟に用意しても良い。」
「そのような生活など、誰も望んではおらぬ。」
睦月はゆっくりと立ち上がった。
「失礼する。」
帝は立ち上がりゆっくりと出ていく睦月を黙ってなす術もなく見つめていた。
「兄様〜!帝のおじちゃんは何の御用事だったの?」
畝傍の山の麓にある睦月の掘建て小屋で、末の弟の師走が睦月の帰りを出迎えた。
「うん、お薬の話をしにいっただけだ。」
「ふうん。」
師走は白湯に裏庭で摘んだ草をいれて、睦月に差し出した。
「ねえ、兄様、今日変なおじちゃんが来たよ。」
「変なおじちゃん?」
「立派な服を着たおじちゃんが、兄様と立派なお屋敷に住まないかって。どうやら僕らがアマテラス様の子だって知ってるみたいだった。」
睦月は少し顔をしかめた。
「それでなんと答えたの?」
「僕らアマテラス様から日の屋(太陽)っていうすごいお屋敷もらってるから、そんなのいらないやって言った。」
睦月はにっこりと笑って、師走の頭を撫でた。
「ここも騒がしくなってきたな。」
「おひっこし?」
「そうだ。」
「今度はどこに行くの?」
「香具山の麓。すぐ近くだ。準備はいいか?」
「うん。作ったお薬は全部持ったよ。」
睦月は野山に分け入り、師走とともに薬草を摘み、それを加工して薬を作る仕事をして過ごしているのだ。今のような冬場は特にそれを干したり砕いたりして、薬を作り貯蔵する。また、冬の間にとれる薬草や、魚からとれる肝油からも薬を作っているのだ。それを直接人々に売る事もあったが、大抵は弟の医者である如月に渡し、役立てる事が多かった。
睦月はゆっくりと手を広げた。そして、ゆっくり指をぱちん、とはじいて澄んだ綺麗な音をたてた。
ぽうっ…
微かな音と共に、草で葺いた屋根の粗末な小屋に、小さな火がついた。
ぱちん…。
再び指の鳴る音がした。ごうっと言う音がして、その炎は天に向かい一筋の柱になった。
ぱちん…。
3回目の音と同時にこの炎は突然静かになり、小屋は跡形もなく消え去った。
「さあ、いくよ、師走。」
「はあい。」
「ああ!!」
数日後、今度は自ら牛車でこの畝傍の麓にある睦月の小屋に足を運んだ帝は、自分が大きな過ちを犯した事を知った。そこにはすでに跡形もなくうっそうと木が生い茂り、こちらに向けて焼けこげた大きな木のうろがポッカリと口を開けていた。
「日暦…。この都にいてくれれば良いが…。」
帝は力なくうなだれると、再び牛車にのり、お屋敷へと帰っていった。空にはあいにく太陽は見当たらず、分厚い雲がその輝く屋敷を覆い隠しているところだった。
「余は八百万の神のお力を失ってしまった…。余の治世も終わりが近いやも知れぬ。」
その後、都は再び流行り病と飢饉が襲い、付け火も相次ぐ様になった。そして翌年、帝は急な病に倒れられお隠れになったと言う。
 |
 |
|||||||||
| 招待状 | 掲示板 | |||||||||
| 日暦トップ | ||||||||||