
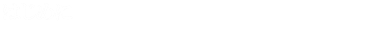

白石和紙工房での紙干し風景
蔵王山に初雪が降り、山すその白石地方は田畑の刈り取りも終わった後、冬至がすぎると紙漉き農家は忙しくなります。
宮城県の南端・白石市を中心とする七ケ宿町、蔵王町の1市2町は旧刈田郡に属し、江戸時代には、伊達政宗の領地でした。そのうち1万8千石を家臣・片倉小十郎が所領していました。
ここは東北地方のノドのような地形で、国境を守るため多くの家臣を抱えていた上、山の多い場所で田んぼが少なく、また奥州街道と羽州街道の本街道が2本貫通し、奥州9、羽州13の大名が参勤交代のため1年ごとに通行し、荷物の搬送に多くの人馬を要するところでした。
そのため、「裸で茨(いばら)を背負うか、鉈で頭を剃るか、刈田で百姓をするか」という言葉があるほど、侍も農民も苦しかったのです。ここに多くの物産が生み出される要因がありました。
江戸時代には、温麺(うーめん)、葛粉、生糸、和紙、紙布、紙衣、紅花などの産物があり、特に温麺、和紙、葛粉は「白石三白」と言われて、品質の優秀さは全国に知られていました。
白石和紙は、和紙そのものの良さで有名でしたが、その和紙を使った衣類、つまり紙衣(かみごろも)や紙子(かみこ)と呼ばれる加工品や、和紙を糸にして織り上げる紙布織りといった、独特の紙文化を発展させました。
平成27年5月に、長年白石和紙を担ってきた「白石和紙工房」が高齢化のため生産を終了。蔵富人が、「ふくよかに、きよく、うるわしい」みちのく紙の生産技法をそのまま継承し、漉き続けています。
また、吉見紙子工房、佐藤紙子工房では、丈夫でふくよかな白石和紙は、版木にのせて模様を打ち出し、柿しぶ、くるみなどの天然染料で染色され、札入れ、名刺入れ、ハンドバックなどに加工されています。
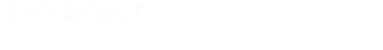

復元された白石城
みちのくに紙
陸奥国の紙が記録に現れるのは平安時代中期以後。清少納言や紫式部らが枕草子や源氏物語などの中で書いています。それによれば、みちのく紙は、ふくよかに、清く、うるわしく、気品のある格調高い紙でした。香を焚き込め、手巾がわりに用い、水に濡れても丈夫であり、ものを書くだけでなく実用性を備え、まことに愛好すべき紙であると賞賛されていました。
産地はわかっていませんが、原料の適作地で水質がよく、陸奥国府に近い阿武隈川沿いの伊達・信夫・伊具・刈田地方あたりであろうかと研究家は推測しているようです。
往来した紙漉き人達
白石地方は、慶長5年(1600)の関ヶ原の戦い以後、伊達政宗の領地となった所ですが、その直後から続々と紙漉き人が各方面から入ってきます。記録に明らかな主なものは通りです。
小関藤兵衛-羽前国(山形県)松森の紙漉き人で、文禄年間(1592~5)以来、伊達家御用の杉原紙を漉いた。慶長6年、中目村北屋敷に移住してきた。
小林丹波-慶長9年の文書では、白石の杉原紙漉き人小林丹波及び中目の小関藤兵衛に知行地を与えている。
高野出雲-代々伊達家の御用紙漉き人であった。天正19年正宗に従って岩手県に移り、良質の水を探し求めて刈田郡沢内村(蔵王町宮)に移住してくる。慶長5年以後間もない頃であろう。伊達家及び片倉家の御用紙を漉いた。
越前紙漉き人藤松・吉二・次久-越前国朝倉旧家臣である上西藤左衛門が慶長7年に刈田郡才川村に来て、10年に白石本町に移住。11年に仙台藩の納戸方用達を命じられ、藩の中では紙漉き人が少ないので越前国五箇村の紙漉き人3名を招き、紙を漉かせた。中目村銭坂に紙漉き製造所を建てたと伝えている。
製紙地としての条件
これらの人々が新しい領内に入った時、製紙に最も適当な土地を探して移り住んだのですが、その条件としては、1つに原料の楮(こうぞ)の栽培に適した土地であること。第2に良質の水が豊富であること。第3に紙漉きを行う冬期間、晴天の日が多く、空気が乾燥していること、があります。
白石の場合はどうでしょうか?
・地質が火山灰質で楮の栽培に適している。地形が山地で傾斜が多く、植栽面積が広い。
・水質が適している。小関及び越前衆はともに良質のわき水地帯・中目に住んだ。
・藩の南部にあって冬でも比較的暖かく、積雪量もあまり多くない。
・冬期間、晴天の日が多い。同じく空気が乾燥して紙干しに適している。
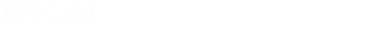

紙布織の数々
紙布とは、和紙を細く切り裂き、丸くしてつないで糸にしたものを織物に使うもので、たて糸に木綿、よこ糸に和紙をつかって織るのを「木綿紙布(もめんじふ)」、たて糸に絹、よこ糸に和紙を使って織るのを「絹紙布(きぬじふ)」、たてよことも和紙を使って織るのを「諸紙布(もろじふ)」といいます。
白石で紙布織りが始まったのがいつなのか、分かってはいませんが、万治2年(1659年)には文献に出てくるので、それより少し前だと言われています。最初は平織や雲才織という足袋底などにするじょうぶな織り方の紙布でしたが、江戸中期には伊達家から将軍家や京都の公家、大名への献上品となりました。
紙布織は武士の内職として始められました。紙子と同じように、東北は木綿が少なく貴重だったので、武士でも紙子や紙布を着るように命じられていたのです。
■紙布織の作り方■

流し漉きで繊維を縦にそろえる漉き方で漉いた和紙を折り、上下を少し残して細く裁断します。
2.紙もみ(写真2.3)
裁断した紙を広げると、上下を残して中だけ切れています。広げたあと縦に5つ折りにして紙を湿らせ、ブロック(遠藤和紙工房では凸凹のある大きい石)の上に乗せて手で静かにもむと、糸状になります。
3.糸うみ(写真4)
糸もみのあと、上下に残した紙を一本の糸になるように注意深くむしり取ります。上、下と続けていくうちに、だんだんと長く1本の糸になっていきます。次の紙になったとき、端の部分を開いて人差し指の上にまたがせて、次の糸の端を中に入れ、丸め込むとまた続きの糸ができてきます。こうして長い和紙の糸を完成させていきます。
4.よりかけ(写真5)
糸車にかけてよりをかけます。
5.機織り
機織り工程は、一般の手織機と変わりはありません。ただ、紙は縮み類が多く、1尺6寸前後の幅広に織りました。
白石では今、紙布織りを専門に行っている人はいません。なかなか手間がかかる分、高価なものになってしまう紙布は、需要があまりないのが現状です。


|
こうぞ切り こうぞの株から黄色な太根を掘り出し、10センチぐらいの長さに切って、苗木にして畑に伏せておくと新芽が出ます。2年目にそれを本植えし、根を張らせて3年目の落葉後、冬至を過ぎてから切ります。
|
|---|---|

|
こうぞこしらえ こうぞ切り取って、1年ものと、2~3年の古木とは別々に束ねてきます。運んできて、束を解いて1本ずつ刀で小枝を切り払い、蔦なども除きます。 |

|
こうぞ蒸し 工房の広い土間の片隅に直径1mほどの大きな釜をかけたかまどが作ってあります。細い丸太を十文字に編んだ格子を釜の上に乗せ、その上にドーナツ形に藁を編んだつばを乗せ、釜に水を汲み込みます。
|

|
こうぞ引き 干した黒皮を束ねたまま 一夜水に浸して全体を再び湿らせます。
|

|
白皮乾し 白皮は剥いですぐ干します。特別に白い紙にするため、雪にさらす方法もあります。積もった雪の上に、濡れたままの白皮をばらばらまき散らしておくと、繊維と繊維の間に含まれている水分が凍るため、繊維がよくほぐれ、太陽と雪の強い紫外線にさらされて真っ白になります。自然の中で漂白したのは、薬品で漂白したのとは異なり、繊維も痛まなず、暖かみのある白さになります。これを「雪ざらし」といいます。 |

|
草洗い 干した白皮を清水に浸してざぶざぶ振り動かしながら、ごみや黒皮を洗い出し、ざるに入れて水に浸しておきます。使う量に応じて年中行われるので、寒い冬時はここで働くおばさんたちは大変です。 |

|
草煮(くさに) 干した白皮を清水に浸してざぶざぶ振り動かしながら、ごみや黒皮片を洗い流してざるに入れて水に浸しておきます。 |

|
草出し 草煮した「かみくさ」(草煮を終わった白皮の呼び名)を、翌朝釜から上げ、ざるに入れて流水の中に浸す。着物をどっさりと着込んだおばさんたちが水辺の台に座り、ざるの中にかみくさを一本一本指先で引き上げながら、白皮に残っている芽の固い部分や変色した部分、きずの所などを注意して指先でちぎり捨てます。黒皮やごみも捨てます。白皮は煮られて柔らかくなっているので、あまり強く洗い流しません。 |

|
草打ち 草出しを終わった紙くさを両手で大きく丸めたぐらいの分量を取り、厚い板台の上に乗せ、角長の木のたたき棒でたたきます。一人でたたいたり、二人で向かい合ってたたいたりします。この作業は繊維をたたき切るのではなく、紙くさの繊維の一本一本をほぐすためなので、鋭い刃物は使いません。 |

|
ざぶり 幅1m、横と深さ各60センチほどの木箱に清水を汲み、叩き上げた紙くさを入れ、大きな櫛のような「馬鍬(まぐわ)」という道具を強くざぶざぶと前後に動かして、繊維を完全に一本一本ばらばらにほぐしてしまいます。水の中は白い綿のようになります。この中に手を入れて静かに動かしながら、黒皮の残りかすや繊維の荒い所などの細かいごみを針の先で丁寧に拾い出します。
|



|
紙漉き 紙漉きの道具 |

|
紙床(かみどこ) けた休めの木を左右から引き寄せてけたを乗せ、金具をはずして上けたを開き、すきすの手前と先端中央部を持って、簀(す)をけたからはずし、そのまま漉き手は180度回転して後ろを向きます。そこに敷き台があります。
|
|
紙くれしぼり 紙床は「かみくれ」ともいいます。一日の紙を漉き終えたあと、紙床を水切り台に移し、上へ木の板を乗せ、万力(ジャッキ)をかけます。翌日紙漉きをしている合間に、少しずつ万力をゆるめながら一日がかりで水を絞り出します。この時急に力を加えて絞ると、片端から崩れて流れ出し、紙床全部がだめになってしまうのです。 |
|


|
紙乾し 水気を切った紙は、晴天の日を待って干します。屋外で太陽の直射日光で干すのが良いです。
|

|
紙断ち仕上げ 戸外の太陽光線で干し上がった後、干し板を作業場に取り込んで、1枚ずつ丁寧に干し板からはがします。晴れたり曇ったりでも紙の白さは異なります。剥がした紙を裏表をそろえ、厚さの同じようなもの、白さの同じようなもの、痛みやしわ、破れ、波紙などそれぞれに選り分け同じ質のものをまとめます。50枚漉いても全部同じ調子の紙というわけにはいきません。
|

