2.参加者のコメント・感想
以下は、参加した会員の方のコメント・感想です。
(タイトルにつてはこちらでつけさせていただいたものもあります。)
 ツービー湖の歌会見学旅行に参加して I.S ツービー湖の歌会見学旅行に参加して I.S
本会創立時の第一回研究発表会後、懇親会の席上で会長の工藤さんに是非白族の歌垣を実際に見学する旅行を計画してくださいとお願いしたことがあった。これは少し虫のいい無理なお願いだとは思いながらも、その後かすかに期待してもいた。それが、思いの外はやく実現することになった。旅行の手配をしてくれた工藤隆さん、岡部隆志さんにまずもって感謝申し上げなければならない。また、本来ならばこうした不案内の土地の旅行にはさまざまな困難や苦労が伴うはずであるが、今回は緻密周到に按配してくれた中国側の案内者、雲南大学の張正軍さんのお蔭で、我々一行は実に快適な旅行をすることができた。
さて、今回歌会が行なわれる地を実際に訪れてみて、そこが白族の複合的な聖地の一つであることが明確に実感できた。場所は、雲南省大理市の北々西にあたるジ源県のツービー湖岸。ツービー湖は、周囲を数百メートル以上はあろうかと思われる山々が取り囲んでいるが、その山の北西部に一部の尾根が次第に低くなって湖水に少しだけ突き出したようになっている、そこが今回訪れた羅谷山と呼ばれる歌会の現場である。祭祀の中心となっているのは湖面から少し高台に建つ竜王廟であるが、観音菩薩や山の神といった他の神仏も同時に祭祀の対象となっていることから見れば、ここも白族の本主信仰の地と考えられるように思う。そして注目すべきは、この地の祭祀施設や祭祀行為の場所が湖底から山頂まで見事な階層性を成している点である。
まず天上界に近い方から数えると、山頂には観音堂①がある。このお堂は常に老女たちが参拝する所だともいうがこの日前後はとくに線香の煙が絶えなかった。そこから半分ほど下った山の中腹にあるわずかな平坦地の幾つかの拝所②では、白語でサイヨウと呼ばれる女性シャーマンの仏寄せが行なわれていた。男女の歌の掛合いが行なわれていたのはだいたいさらにその下方、梅林のあるなだらかな傾斜地③であった。竜王廟の建物④はまたさらにその下、湖面から二~三十メートルほどの高さと思われる場所にある。この高さの場所ではほかに男女の歌の巧者たちによる掛合いのど自慢や女たちによる踊りも行なわれ、縁日に付随した芸能の場ともなっている。また、この地の人々の観念によれば、湖底には洞穴⑥があって、祖霊の世界⑦に通じる通路となっているのだという。簡単な概念図を描いてみれば、次のようになる。
_①_観音堂
_②_/ 巫女の仏寄せ
_③_/ 梅林の歌会
_④_/ 竜王廟(屋台の飲食・芸能の場)
_⑤_/湖上の水面(灯篭流し)
_⑥_/ 湖底の穴(他界への通路)
_⑦_死者・祖霊の地下世界
我々の訪れた八月末日は年に一度の竜王廟の縁日で、廟の周囲は多くの参詣者たちでごった返していた。廟の門を入ると中庭になっていて、そこには食事持参の婦人たちも大勢いたが、その外には沢山の屋台も出ている。お祈りも廟内だけではなく、山の斜面のあちこちに拝所があって数珠を繰りながら小さな打楽器を打ち、線香を焚いて祈る婦人たちがいた。ここは、仏寄せが行なわれるように、死者の霊魂とも出会える場所であり、山全体が聖地だという印象を受けた。夜には、漢民族の風習が入ったものといわれるが、湖上で小さな灯篭を流す行事も行なわれている。暗い湖面に浮かぶ小さな蝋燭の光の群れを見つめていると、その日は死者たちの霊が他界から帰ってきたように感じら、この日この地では死者との出会いが容易に行なえるときなのだと納得させられる。そしてまたここは、各地から徒歩で集まってくる世俗の参詣者たちの出会いの場ともなるのである。
竜王廟の横では、仮設の櫓の上で、スピーカーの音量を上げ、のどに自信のある男女の模範的な歌の掛合いが行なわれていた。それが雰囲気作りとなって実際の男女の歌掛けを誘うかのようだった。いわば、この日の男女の出会いは神によって認められ、歌会という制度によって保証されている。
八月三十一日の夕方、帰りがけに民族衣装の晴れ着を着た若い女性と、ブレザーを手に持ったワイシャツ姿の青年との白調による歌掛けを実見した。我々はこれをこそ見たかったのである。その歌詞は後日工藤氏によって発表される予定であるが、この一件だけでも今回の歌会調査は有意義な旅であった。二人は十メートルほどの距離を置いて歌を掛合っていた。ともに既婚者だといい、二人の住む村と村とは二キロメートルほど離れているらしい。女性は子連れでもあった。ここに、万葉集巻九・一七五九番、高橋連虫麻呂歌集の「筑波嶺に登りてカガヒを為る日に作る歌」そのものの世界があったことに驚いた。実際に見ないうちは分からないことも多かったが、その一つ、歌の掛合いは個人的な空間において行なわれるのではなく、衆人環視の中で行なわれることが自分の眼で確認できた。男
女が掛合う歌の中にも、周囲に多くの人々が見ていることを前提にした内容があったし、さらにはまた二人のことが人の噂に上ることを気にする内容の歌詞もあった。これらも万葉集の恋歌を思わせるものである。また、歌の掛合いがどのように終わるのかという点も確認したかったことだが、そのときの例では、歌によって再会を約しつつも、女性の子どもがもう帰りたいと彼女の手を引いたことにあったようだ。他の例でもそうだったが、何らかの形で女性の側がその場を立ち去ることで歌が終結することも確認できた。
現地に同行してくれた工藤・岡部両氏の調査協力者である施珍華さんの話によれば、白族の男女で歌の上手な人は比喩の使用が多いという。(施さんとの会話は遠藤耕太郎氏に通訳してもらった。) ホテルに帰って採録したビデオ映像を確認する作業に同席したとき、私には比喩表現の特徴がとりわけ印象的だった。
・花が高くて手が届かない (近寄りがたい)
・私の友は私の影法師しかいない (独りぼっちだ)
・私たちは花と楊(ヤナギ)のようだ (最良のカップルだ)
・天を蒲団とし地をベッドとして寝る (野宿する)
・生の米をご飯に炊く (娘と関係を結ぶ)
などなど、文字を持たず即興的に歌われる巧妙な比喩表現による歌は彼らの立派な口誦文芸であることを認識させてくれる。
施さんもまた若いときは歌掛けの名手であったという。歌掛けの歌は、一定の節廻しを単位として、それを男女で交互に繰り返してゆくだけである。しかしそれゆえ即興の歌詞に意識を集中することができる。歌詞の内容は、相手の歌に対して当意即妙に紡ぎ出されなければならない。施さんは歌を村の老人たちから習ったという。立ち話だったので音楽性をいうのか歌詞をいうのか分からなかったが、歌掛けに出ようとする者は、ふだん野良仕事をしながら練習に励んでいるのだとも教えてくれた。施さんは民族楽器の三線も弾け、音楽方面にも明るい方である。前述の若い男女の歌掛けの場には、歌う青年の横で途中から三線の伴奏を付ける男まで現われたのだが、その三線の調弦が気になったので尋ねてみたところ、白族の三線は低音の弦から四度と五度の音程で調弦されているとのことであ
った。第一弦と第三弦は八度即ち一オクターブの差となっており、この調弦法は日本の三味線でいうところの本調子に等しい。中国の三線が本調子であることはすでに知られていることではあるが、白族の調弦法もまたその例に漏れないことを確認できたことが私にとっては収穫であった。因みに、ツービー湖歌会で用いられていた三線は、胴の形がほぼ正六角形、海老尾に当たる部分は表向きに竜の顔が彫刻してある。竿は三味線よりも少し短く、弦を弾く指にはドングリの実のような形のピックをはめていた。
三線のついでに言えば、竜王廟の縁日の会場に入る門の付近にいた若者たちの中にこれを弾きながら歌掛けの歌を一人で歌い興じていた若者がいた。歌詞の内容は確認していないが、時々廻りの青年たちが笑うところをみると、彼もまた即興の歌詞を作って歌っているらしく思われ、この地の歌の在り方の今一つを見る思いがした。
ところで施さんによれば、歌会の歌には白調ともいうべき伝統的な節回しがある一方、漢民族風のという意味で漢調と呼ぶべき節回しがあるともいう。この地の歌会はさまざまな様態をもって行なわれている。
八月三十一日の午後は、我々一行が各自思い思いに歌会の会場を歩き廻って歌掛けする男女を探すことになっていた。私は一旦山頂の観音堂まで登り、そののち下の梅林近くまで下りてきたとき、ユーカリの木の下に数人の男女が座っていて歓談しているのに出会った。近付いてみると、何とその中の二人が歌の掛合いをしていたのである。初めて出会った歌垣の光景だったこともあって、私にとってはこれも大きな衝撃であった。ビデオカメラを向けるとこちらを気にするふうだったので、私は彼らのすぐ横に座を占めながら、何と無く良心が咎めたが気付かれないようにしてカメラを廻し続けた。男五人女三人の集団で、歌を掛合っているのはそのうち一番若い男女であった。他は比較的年長者だった。一緒にいた他の男女は二人の歌掛けを、各自勝手な行為をしながら、聞き入るともなく聞い
ている。掛合いの始りは分らない。二人は始め間に二人ほど置いて離れて座って掛合っていたが、しばらくすると娘は立ち上がり、若者のすぐ近くに腰を降ろして掛合うようになった。そのときはもう自分たちだけの世界のようになっていた。娘の方は少し照れ臭そうに、草の葉をいじりながら顔を少し背けて歌っている。そんな彼らのすぐ横の草むらに座って、私もまたあらぬ方を向きながら無関心を装いつつ、しかし胸中は初めての歌垣の現場との遭遇に感動しつつビデオをとってきたが、残念ながら後で見てみると廻りの音に消されて声が小さく良い資料とはなっていなかった。聞けば、この例は白調ではなく漢調の歌掛けのようである。しかし晴れ着を着て半ば人々に聴かせるように高らかに歌い合う歌掛けと異なり、会場の片隅で静かに普段着のままで、しかも多分実際の恋愛と近い気分の中で行なわれる点では、これも貴重な事例だったと思う。
ツービー湖竜王廟縁日における歌会はこのように幾つもの異なる様態が見られることはすでに工藤・岡部両氏著『中国少数民族歌垣調査全記録』に述べられている通りではあるが、また前述のようにこの地が複合的な祭祀の場としてもあることを考えると、ここをさらに総合的に調査研究する余地がありそうに思えてならない。(了)
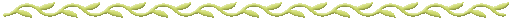
 三つの課題 N.I 三つの課題 N.I
9日間という駆け足の旅ではあったが、こんど初めて雲南に足を踏み入れる機会を得て、多くの刺激を受け、自分の興味もぐっとひろがった。そのなかから、今後考えていくべき課題も少し見えてきたように思うので、以下、3点に分けて記しておきたい。
まず第一は、歌垣の調査研究における「観客論(オーディエンス論)」という視点の重要性ということ。ツービー湖海灯会での歌垣を観察していていちばん気になったのは、そこでの歌の掛け合いがつねに第三者(観客)の視線を前提として展開していることだった。したがって、歌垣のことばを「うそ」と「ほんと」の二分法で考えるのは生産的ではなく、むしろ、龍王廟の参詣やシャーマンの口寄せ、各種の舞踊、スピーカーを通したセミプロの歌の掛け合いの実況、夕闇の湖上での精霊送りetc. などが組み合わさった演劇的な空間としてとらえることが大事だと感じた。
次は、「少数民族」という概念のことだが、これを実体的・固定的なものと考えるのは大変問題で、民族としての帰属意識や保存される伝統文化も、国家の側からする法的・制度的な特権付与等々の政策と密接にからまりながらできあがっていること、そしてまた、そうした少数民族の存在が、逆に「漢族」という優越民族の存在を一枚岩の自明なものと思わせているという点である。「民族」の問題が決して過去の問題ではなく、現在進行中の問題だという、あたりまえと言えばあたりまえの事実を、あらためて再認識したしだい。
最後は、これまでの雲南論の見直しの必要性だ。初期の鳥居龍蔵の調査においても戦後の照葉樹林文化論においても、われわれは雲南を「鏡」として日本人としての自己像を確認してきたところがある。そういう「鏡」の機能を負ってきたもろもろの雲南論を全体として検証することが、このへんで本格的に試みられねばならないと思った。
いずれの問題も、個人で引き受ける課題としては大きすぎる。いろいろなレベルでの共同調査・共同研究が企画される必要がある。
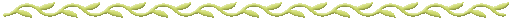
 歌声の響き渡る丘 N.K 歌声の響き渡る丘 N.K
向かつ尾上に立つ乙女。こちら側の峰には男。向かい立つ二人の間で歌は谷を越えて一筋に放たれる。記紀や万葉の記録から描き出した、こんな歌垣のイメージはわずか二日間の、ささやかな実見によってあっけなく打ち砕かれてしまった。雑踏の中で互いに笑いふざけながら楽しそうに歌を掛け合う老人たち。丘のはずれの四阿のごとき小さな小屋の中では、男女のグループが机を挟んでひしめきあって座り、中の二人が少し恥ずかしそうに歌を交わしていた。木の下に座りながら歌い掛ける男女もいれば、立って木の枝に手を掛けて歌う女もいる。その場所も、歌い手たちの姿勢も、二人の距離も、実に様々で、そこには何ら決まった作法などなきがごとくであった。何より印象深かったのは、歌い手たちが、互いに凝視めあうことがないことだ。男も女も、互いの顔を見、眼を見て歌おうとしない。寄り添うように腰を下ろしていた若い二人など、歌うたびに横ぞっぽを向いて、あたかも誰もいない中空に向かって歌い放つかのようであった。
それにしても歌声の響き渡る丘の上から見た?碧湖は美しかった。緑の山と空と。人を歌へと駆り立てるような何かが、そこには確かにあるような気がした。
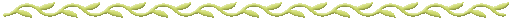
 常世郷を訪ねる M.R 常世郷を訪ねる M.R
この夏のアジア民族文化学会の見学旅行のお陰で、漸く長年の胸の支えを下ろすことができた。以前、照葉樹林文化圏についての学説を読んでから、実は、ずーっと、いつか雲南に行ってみなくてはと思い続けていた。僕にとっては、万葉びと憧れの常世郷みたいな地の一つが雲南だった。常世の国は、やはり常世の国であった。標高2000米の地に青い水を湛えたツービー湖をゆっくりと渡し船で梨園の中の白族の村にたどり着いたときの、あの不思議な感覚。異質な空間、異質な時間の経験ということになるのだろうか。
そして、また、祭りの庭でのあの歌垣。廟の中では、道士めいた老人が竜王に壽詞を読み上げている。裏の梅林の一角では、死霊の憑依したシャーマンと、涙にむせぶ死者の家族達。また、別の梅の木のもとでは、おそらく歌に長けたであろう中年男女の芸能的な歌の掛け合い。あるいは、また、無意識に身近な梅の枝を手折りながら、懸命に歌詞を捻り出そうとする若い娘。あの生の歌垣の場を、簡潔に整理することはできない。
ただ、一つだけ、はっきりしていることがある。一方に、祖先から伝承してきた通りに口ずさまなければならない場と表現形式があり、一方に、独創的で即興的であることが許容される場と表現形式があるという問題である。唐突であろうか。今、このことを分かり易く説明することはできない。しかし、僕にとって、重要な実感であった。もし、いつか、うまく説明する事が出来たとしたら、梅が枝手折る、常世の国のあの乙女と、浦島を背に乗せて案内するが如く、かの地を先導して下さった方々のお陰である。この場を借りてお礼申し上げる。
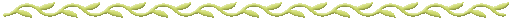
 日本の古代について考えた O.S 日本の古代について考えた O.S
快晴とさわやかな風、それに美味しい中国料理を山盛り。雲南旅行は、快適の一語でした。旅行中お世話になった皆さん、どうも有り難うございました。
昆明を出発して、まず驚いたのは、二千メートルを越える山岳地帯を走る真新しい高速道路だった。それに平行して走る田舎道が、戦争中に開かれた援蒋ルートだと、工藤さんから教えられた。日本軍を敗北に導いた歴史的な道路だ。しかし、半世紀前までは、雲南の山岳地帯は険峻で、中国の文化を寄せ付けず、お陰で、文字も国家も持たない素朴な少数民族の文化が今日に残ったのだろう。
南詔国の故地大理からじげん(漢字の地名)へ、そしてつーびーこ(漢字の地名)の歌垣の見学は圧巻だった。地形も、筑波山の中腹とよく似ており、誰しも常陸国風土記の歌垣を連想したに違いない。民族衣装を着た女性を中心に、延々と美しい旋律の歌声が交わされる。牧歌的で、ユーモアもありながら真剣な男女の掛け合いが、人間としての原点なのだと思った。
旅行中、日本の古代についても考えた。中国文明と海を隔てた日本は、文字を覚え、たちまちに権力社会を築いた。そのため、多くの試行錯誤も生じたのではないか。
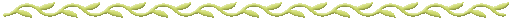
 「東アジア人」としての自分 I.H 「東アジア人」としての自分 I.H
アジア民族文化学会から雲南の歌垣調査旅行の計画が出されて、中国へは以前から行きたいとは思ってはいたが、現在私は博士論文の作成中で旅行なんか行っている場合ではないという状況だったので非常に悩んだ。しかし、今回行かないと中国には一生行けないような気がして、無理をして行くことにした。ところが、雲南から帰ってからは、すっかり、中国かぶれになってしまったし、一生通い続ける(一層住み着くかも?)ような気がした。私は今回の旅行で自分が「東アジア人」であることを強く認識させられたが、それは、私が韓国生れで、現在日本に住んでいて、両方の国についてある程度知っているし、それでまた雲南を体験することができたので、多方面(文化、民族、文学その他)において三国の比較ができ分かりやすかったし、とても楽しくて面白かった。
個人的に雲南で特に気に入ったのは食べ物である。今回は団体旅行で、大勢で円卓を囲んで食事をしたので、色んな種類が食べられたので、特別よかったとおもう。野菜が豊富で、南の方なので味が塩辛くなくで、とにかく気に入った。雲南ではよく食べたので、まさに医食同源という言葉通りで、旅行から帰っては旅行疲れもなく翌日から日常の研究生活に戻れたし、旅行前より健康になっていた。
歌垣の現地では、歌垣は勿論、白族のシャーマンのことも見られてとても有意義だった。日本に戻って一時は、頭の中で中国語・日本語・韓国語・英語が交通整理がつかなくなって、日常の会話の中でいろんな国の言葉が思わず口から飛び出てしまったりした。私は今回の旅行で人生変わりそうな気がする。
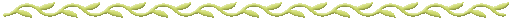
 多様な雲南文化 M.Y 多様な雲南文化 M.Y
この夏、アジア民族文化学会主催の雲南歌垣見学旅行に参加した。ここ数年人身供犠や食人の研究をしてきた私は、鳥越憲三郎氏の首狩り研究に触発されて、かねてより雲南には是非行ってみたいと思っていた。そんなときにこの好機にめぐり合い、歌垣についてはまるで素人であるにもかかわらず参加させていただいたのである。
そして、私は、この旅行に参加するにあたって、もうひとつ公的な使命も負っていた。それは、私の勤務する東北文化研究センターで今年から始まった「東アジアのなかの日本文化に関する総合的な研究」という5年間のプロジェクトで、雲南も調査地の候補のひとつにあがっていたので、その予備的な調査をして報告することであった。
そして雲南へ。9日間の旅は実に刺激的で興奮の毎日だった。ペー族の村の本主廟で目にした鶏や豚のいけにえ。歌垣会場で聞こえてきた耳にここちよいかけあいのメロディ。華やかな歌垣の陰で、人々の涙を誘っていた巫人による仏おろし。そして、博物館で見たバラエティに富んだ民具や民族衣装の数々。研究調査どころではない。ほとんど旅行者の感覚で目にし耳にするものすべてに興奮していた。
ところが、帰国して、いざ報告という段階になったとたん急に頭のなかが混乱してきた。雲南の文化の多様性をどのようにとらえたらいいのか、整理がつかなくなったのである。25以上もある少数民族をかかえる雲南では、南部に住む民族には明らかに沖縄につながる文化要素が含まれているし、北部に住む民族の生活文化には、アイヌや東北につながる要素がみられた。すなわち、そこには「雲南」というひとくくりの文化など存在せず、いくつもの文化が共存し、重層し、複合して、そしていくつものルートを通って日本列島の南/北に辿りついたのだと思われるのである。考えてみれば当然のことではあるのだが、私自身が「ひとつの雲南」という幻想を無意識のうちに思い描いていたことに気づかされたことは、今回の見学旅行における大きな成果であったように思う。
だが、これからがたいへんだ。5年間のプロジェクトのなかで、実りある共同研究を進めていくには、いくつかのテーマと地域に焦点をしぼり、事前にかなり緻密な計画をたてなければならない。現在考えているテーマは「焼畑」と「色彩」についての比較研究だが、今後、学会のみなさんにもアドバイスとご協力を仰ぎ、プロジェクトを成功させたいと考えている。
最後ではあるが、この見学会を主催し、ご自身の貴重な調査の時間を割いてまでも旅行者気分の私たちを導き、根気強くつきあってくださった、工藤隆氏、岡部隆志氏、遠藤耕太郎氏、そして雲南大学の張正軍氏に、心から感謝を申し上げたい。
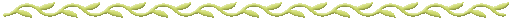
 未知の世界に接して I.M 未知の世界に接して I.M
歌垣については、かつて奄美大島に2度ばかり勉強する機会があって、いわゆる行事の時に行われる集団的掛け合いと、数人のグループによる座敷での歌掛き遊びは知っていましたが、今回のような不特定多数の男女が、配偶者や恋人を獲得する目的で行われる歌垣に接することが出来たことは、私にとっては大きな収穫でした。
事前の予備知識なしに参加したことでかえってその感動を大きくしたのだと思います。若者も老人も、男も女も集いあい、恋をささやくのではなく、大声を張り上げて集団の場において歌でプロポーズする。『風土記』の世界がそのまま再現されていることの驚きと同時に大変なカルチャーショックを受けました。しかも歌垣に参加しているのは大人たちだけではなく子供も大勢参加しているということも予想外でした。また、歌のリズムも白族独特のリズムと漢族のリズムがあって、歌い手によってそのリズムが同じ歌垣の場面で交じり合うこともありうるということも大きな発見でした。
2日目の歌垣の最後に出会った、妻を亡くしたといっていた男性と情熱的な歌の掛け合いをしていた可愛い彼女のあの2人の若いカップルは、あくる日も歌垣の続きを繰り広げていたのでしょうか。最後まで見届けることが出来なかったのが残念でなりません。あの2人の掛け合いを見ていて、あの若いカップルはきっと近い将来結ばれるのではないかという予感を抱いたのは私1人だけではないでしょう。
いずれにしても、未知の世界に接して得たものはたいそう貴重なものでした。このような得がたい機会をおあたえくださいました工藤先生、岡部先生に心からお礼を申し上げます。もしまたこのような調査旅行に参加できる機会がありましたら、是非参加させてくださいませ。
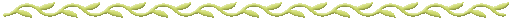
 有意義な旅でした Y.K 有意義な旅でした Y.K
大変楽しく、有意義な旅でした。ありがとうございました。アジア民族文化学会設立2年目の夏、中国雲南省白族歌垣見学旅行をご企画頂き、工藤・岡部・張三先生の周到なご指導と、会員皆様のご援助で無事に目的が果たせまして、厚くお礼申し上げます。
私は直前まで腰痛に悩まされていましたので、妻に叱られ、同室の方に迷惑掛けましたが、宿願の歌垣見学、廟祭と春城の景物に癒され、すっかり元気が戻りました。
まず、目標にある白族対歌の実際が、雨にも遭わずに皆、見られたこと第一。天の恵みと、工藤教授らの開拓的研究のご苦労の賜物と思います。あのツーピー湖畔での歌垣、竜王廟の祭礼と踊りと市、夜の灯籠流しは感動的でした。お祭りのクライマックスの二日午後、私は梅の木陰に佇んだり、行きつ戻りつして、施先生の合図で、あちこちの歌の韻律を堪能しました。ことにホテルで学習会をしたことは、記憶の整理になり結構でした。
第二は、雲南大学で日本語科学生と交流できたことです。一九八三年七月に訪問した時は蚊帳吊りした専家楼に泊まり、金殿や四烈士墓に参拝したりして、第二外国語として日本語はあったものの、日本語学科はまだなく、設置を要望した事を覚えています。街頭には広告が無く、自転車と馬車の雑踏でした。が、今は大発展の日中国交30周年、日本語学科のある大学となり、私は感慨無量でした。
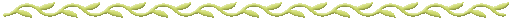
|
|
|